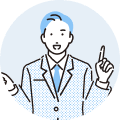- 住宅価格・資金計画
- 2025.9.17
Contents
住宅ローン金利の種類
住宅ローンを選ぶ上で非常に重要になるのが、金利です。ついつい、目先の金利でローンを選びがちですが、借入金利には、主に3つのタイプがあります。
ずっと金利が変わらない=返済額が一定 の「固定金利」。返済途中でも金利が変わる=返済額が増減する「変動金利」。一定期間は固定金利が適用される「固定金利期間選択型」の3つのタイプが主流になります。
ご自分のライフプランに合った、金利のタイプを選択することが大切です。
では具体的に、3つの金利タイプの特徴をそれぞれ見ていきましょう。
変動金利型の特徴

一定期間ごとに金利が変動するタイプ
変動金利とは、原則として半年ごとに金利が見直されるもので、3つの金利タイプのうち一番金利が低く設定されている点が特徴です。ただし、金融政策や経済の状況による金利上昇局面では毎月の返済額が高くなる可能性があり、家計に負担をかける恐れがあります。
もっとも、変動金利は半年ごとに見直されますが、実際の返済額の見直しは5年に一度になります。これを5年ルールと言います。また、5年に一度見直される返済額も、見直し前の額から125%を超えてはならないという125%ルールが設けられています。
ただし、最近のネット銀行では、5年ルールや125%ルールが適用されない場合もありますので、変動金利を選ぶ際には注意して選択しましょう。
また、変動金利には「未払い利息」が発生する可能性があることを覚えておきましょう。
未払い利息は、急激な金利上昇局面で起こるもので、返済額の見直し時に利息額が返済額を上回る部分を指します。未払い利息の額が多ければ、元本部分の返済が終わっても利息部分の返済が終わらない可能性があります。
固定金利型の特徴

借入から完済に至るまで、全期間同じ金利で返済するタイプ
全期間固定型タイプの代表的なものが、住宅金融支援機構が提供する「フラット35」です。
返済開始から完済まで毎月の返済額が変わらないため、返済計画が立てやすいというメリットがある反面、3つの金利タイプの中では一番金利が高い点がデメリットです。また、金利下降局面において、変動金利のように金利の引下げといった恩恵が受けられません。
ただ逆に、金利が上昇する局面においては、いくら金利が高くなったとしても返済額に影響がないという安心感が得られる特徴があります。
固定金利期間選択型の特徴

一定期間の金利を固定するタイプ(期間終了後は、その時点の金利水準で、変動金利型に移行するか、再び固定期間を設定するかを選択)
固定期間選択型とは、最初に2年や3年、5年、10年などの期間を決め、その間は固定金利が適用されます。固定期間が終了した後は、原則として変動金利が適用されますが、多くの金融機関では固定期間終了後、固定金利も選べるようになっています。ただし、適用される金利は固定期間が終了した後のものになるので、そのときの値動きによって適用される金利が高くなる可能性もあります。また、固定期間終了後は金利優遇幅が小さくなるため、総返済額が高くなる可能性がある点にも注意が必要です。
固定期間選択型は変動金利より高い金利が適用されますが、全期間固定型よりは金利が低い点がメリットです。
また、一定期間固定金利が適用されるため、その間の返済額が変わらないことから、子どもの教育費など住宅ローン以外で支出が発生する人などに向いています。
ただし、固定金利期間中は金利の見直しができず、固定期間が終了するたびに変動金利か固定金利のいずれかの選択が必要です。また、固定期間終了時には変動金利の125%ルールが適用されないため、返済額が高くなる可能性もありますので注意が必要です。
2025年の金利相場
2025年1月に日本銀行が追加利上げを決定した影響で、今年の春には多くの金融機関で住宅ローンの変動金利が上昇しました。金融機関によっては0.3%近く上がったところもあり、今後の動向に不安を感じている方も多いのではないでしょうか。
そしてその影響は、すでに住宅ローンを借りている人の返済にも表れ始めています。変動金利で借りている方の多くは、2025年7月の返済分から適用金利が上昇している状況です。
さらに、追加の利上げが検討されているとの報道もあり、「これからどこまで上がるのか?」という点に注目が集まっています。
そこでここからは、2025年の最新の金利状況について見ていきましょう。
変動金利型(0.3%〜1.0%)

引用元:住宅金融普及協会
変動金利で住宅ローンを返済をしている人は、基準金利が上がれば、その上がった分だけ適用金利も上昇します。例えば2025年3月時点の適用金利が0.55%のとき、基準金利が0.25%上がれば、適用金利は0.80%になります。
2025年8月現在、変動金利の相場は0.6~0.7%台となっています。2024年4月時点の金利相場は0.3~0.4%台だったので、この1年で相場は一気に上がりました。
それでは、いつから金利上昇の影響を受けるのでしょうか。
変動金利は、金利が毎月変わるわけではありません。半年に1回、金利が見直されるケースがほとんどになります。
多くの金融機関では毎年4月1日と10月1日に基準金利が見直されて、その2~3ヶ月後から実際の適用金利に反映されます。
そのため、実際に金利が上がるのは2025年7月返済分からという人が多いでしょう。
なお、返済額が5年間一定になる「5年ルール」が適用されている人に関しては、必ずしもすぐに返済額が増えるというわけではありません。しかし、返済額における利息の割合は大きくなります。
2025年の春には、ほとんどの金融機関で変動金利の基準金利が0.25%上昇しました。
なお、楽天銀行は、変動金利の基準が違うため、毎月金利は変動しています。
固定金利型:10年固定(1.5%〜1.8%)

引用元:住宅金融普及協会
固定金利は、多くの金融機関で前月より引き上げられました。引き上げ幅は、10年固定金利の場合は0.056~0.21%です。
固定金利が上がった背景には、固定金利の基準となる長期金利(10年国債利回り)の上昇があります。これは、アメリカの関税措置をめぐる交渉が合意に至ったことで、景気の先行きに対する不確実性が和らいだことが一因です。その結果、日銀が追加利上げに前向きな姿勢を強めるとの見方が投資家の間で広がり、長期金利の上昇につながりました。
全期間固定(35年等)(1.7%〜2.5%)

引用元:住宅金融普及協会
全期間固定金利であるフラット35(借入期間21~35年、団信あり、自己資金10%以上)も1.87%となり、前月よりも0.03%引き上げられました。
固定金利の今後の見通しについて解説します。
固定金利については、10年国債利回りなどの「長期金利」を参考に決められます。
国債とは国が発行する債券で、国は投資家からお金を借り入れて、一定の利子を支払います。利回りとは投資金額に対する利益の割合のことで、償還期間が10年のものが10年国債です。
10年国債利回りは、市場での国債の売買を通じて決まるため、投資家心理や景気の先行き、海外の経済状況などさまざまな要因によって変動します。
日本の10年国債利回りは、2024年秋ごろから徐々に上昇基調に入り、2025年3月末には一時1.59%台まで上昇しました。4月には米国の関税政策への警戒感が強まり、一時的に1.1%台まで急低下しましたが、その後は再び持ち直し、5月には1.5%台で推移する場面が多く見られました。
6月に入ると、長期金利はおおむね1.50%前後で推移し、大きな変動は見られませんでした。
そして、7月に入ると再び上昇基調が強まり、2025年7月23日には、日本国債の売りが広がった影響で10年国債利回りは一時1.6%台まで上昇しました。これは約17年ぶりの高水準です。アメリカの関税措置をめぐる交渉が合意に至ったことで、景気の先行きに対する不確実性が和らいだことが原因で、これを受けて、市場では日銀が追加の利上げに前向きになるとの見方が広がり、国債を手放す動きが広がりました。
では今後、固定金利はどうなっていくのでしょうか。結論からいうと、変動はあるものの、今後も上昇していく可能性が高いと考えられます。
中長期的には日銀が金融緩和の縮小を進めていく方向に変わりはなく、長期金利は徐々に上昇しやすい状況が続くと考えられます。
今後の金利の動き

引用元:住宅金融普及協会
金融機関による住宅ローン契約者の獲得競争は続いています。2025年4~5月には、多くの金融機関で基準金利が引き上げられましたが、一部の金融機関では同時に金利の引き下げ幅を拡大しました。
変動金利型の一般的な住宅ローン商品では、借入期間中は金利の引き下げ幅が一定です。つまり相対的に見ると、引き下げ幅が大きい現在の借り入れの方が有利な状況となっています。
借り換えでも、新規借り入れと同じ引き下げ幅を設定している金融機関も多いです。さらには新規借り入れよりも借り換えの方が金利優遇されていることもあります。
借り換えに関する手数料などを加味しても、金利の差を考えると借り換えをした方がお得なケースが多いといえます。
今後も金利が上がっていく可能性があり、引き下げ幅が小さい方に関しては、借り換えを検討してみるのもいいでしょう。
金利比較のポイント
住宅ローンの金利は、返済期間中の返済額や返済総額に影響を与えるため、自分に合った金利タイプを選ぶことが非常に大切です。
しかし、どの金利タイプを選べばよいのかで、迷う方がとても多くいらっしゃいます。
そこでここからは、住宅ローン金利の基本的な仕組みや、各金利タイプのメリット・デメリット、自分に合った金利タイプの選び方などについて解説します。
複数金融機関での金利比較

引用元:株式会社MFS
住宅ローンを借りる場合には、複数の金融機関を比較検討することが重要です。一般的には、ネット銀行よりもメガバンクの方が低金利に思えますが、ネット銀行では、がん50%保障団信や全疾病保障などが金利上乗せ無しで付帯してくることが多くあります。また、金融機関によっては独自の優遇制度や期間限定キャンペーンを行っていることもあります。
金利だけでなく、団体信用生命保険や事務手数料などの諸条件もしっかり見るようにしましょう。
金利タイプ別コストとメリット比較

引用元:SMBC
・変動金利型のメリット
一般的に3つの金利タイプのなかで当初の適用金利が最も低いことです。また、金利が下がるとそれに合わせて返済額も減少します。デメリットは、金利が上がった場合は返済額も増加することや、あらかじめ将来の返済額を確定できず、返済計画を立てにくいことなどがあげられます。
・固定金利期間選択型
一定期間の金利(返済額)を確定できることです。デメリットは、固定期間終了後の金利や返済額を確定できず、金利(返済額)が上がる可能性があることがあげられます。
・全期間固定金利型
メリットは、完済までの金利(返済額)が確定している点です。そのため、返済計画を立てやすく、将来のライフプランを設計しやすいでしょう。
デメリットは、ほかの2つのタイプより金利が高めに設定されていることが多いことです。また、返済期間中に市場金利が下がった場合でも、適用金利が変わらないため返済額は下がりません。
返済負担率を考慮した無理のない計画

金利タイプを選ぶ際は、ご自身のライフプランを考慮し、無理なく返済できるタイプを選択しましょう。住宅ローンの返済期間は一般的に20年~30年と長期にわたるため、その間に起こる可能性があるライフイベントや家計収支の変化なども想定しながら、無理なく返済を続けられるかどうかを十分に検討する必要があります。
例えば、お子様の人数や大学にまで通わせるかどうかなど、教育費がかさむ期間や、子育てや介護で一時的に仕事をセーブしたりする期間が見込まれる場合には、その期間中は金利が上がらないように固定金利期間選択型や全期間固定金利型を選ぶとよいでしょう。
まとめ
さて今回の記事では、住宅にまつわる「住宅ローン」や「金利」についてご紹介してまいりましたが、いかがでしたでしょうか?
・住宅ローン金利の種類
・2025年の金利相場
・金利比較のポイント
など、大きく3つの観点で、解説してまいりました。
これから住宅の購入や建築を検討されている方は、きっと家づくりのお役に立てる工夫を学ぶことができると思います。
今後の家づくりの参考にされてみてください。
***
まるっと住まいの窓口 では
理想の家を実現するために、
オンライン住宅相談で住宅のプロに中立の立場で直接相談ができます!
また、埼玉、茨城、群馬、栃木エリアで
モデルハウスを100軒以上、家の専門家を100人以上ご紹介しています!
ぜひご活用ください。
この記事に関連したよくある質問
- 3000万円を35年ローンで組んだ場合、毎月の返済額はどれくらい?
-
3,000万円を35年ローンで組んだ場合の毎月の返済額は、金利によって約7万円~10万円程度になります。例えば、リクルートSUUMOによると固定金利1.9%で約9万4000円、変動金利0.5%で約7万9000円となります。
- 2000万円を35年返済すると月々いくら支払う?
-
2,000万円を35年間で返済する場合、月々の支払額は金利によって異なりますが、例えば、固定金利1.9%であれば月々約6.52万円、変動金利0.5%であれば月々約5.19万円が目安です。
- 4000万円を35年ローンで借りると月々の支払目安はいくら?
-
4,000万円を返済期間35年の住宅ローンで借りた場合の月々の返済額は、金利1.5%で約12万3,000円(固定金利1.5%の場合)、金利1.2%で約11万7,000円(固定金利1.2%の場合)、金利0.7%で約10万7,000円(変動金利0.7%の場合)が目安です。金利によって大きく変動するため、具体的な月々の返済額は、ご自身の条件に合った金利で計算する必要があります。
- 住宅ローンの変動金利は一般的に何%くらい?
-
2025年9月現在の住宅ローン変動金利は、金融機関や借入条件によりますが、一般的に年0.6%~0.7%台で推移しており、 ネット銀行では特に低い金利も提供されています。金利は日本銀行の金融政策や長期金利の動向に影響を受け、変動する可能性があるため、最新の金利情報は事前に確認することが重要です。
- 住宅ローンの一般的な金利水準はどれくらい?
-
2025年9月現在の住宅ローン金利相場は、変動金利が年0.6~0.7%台、10年固定金利が年1.6~2.2%台が目安です。ただし、これはあくまで一般的な水準であり、実際に適用される金利は金融機関や個人の信用状況によって異なります。自身の状況に合わせて複数の金融機関を比較検討することが重要です。
- フラット35の金利相場は現在どのくらい?
-
2025年9月現在、フラット35の金利は借入期間21年以上35年以下で、融資率9割以下の場合、年1.890%~4.280%の範囲にあり、最も多い金利(最頻金利)は年1.890%です。ただし、これはあくまで相場であり、実際の金利は借り入れ時の金融機関や加入する団体信用生命保険の種類などによって変動するため、最新の正確な情報は各金融機関のウェブサイトで確認することが重要です。
- 変動金利型と固定金利型、どちらを選ぶべき?
-
変動金利型と固定金利型の選択は、返済額を抑えたいなら変動金利型、長期的な安心と返済計画の安定性を重視するなら固定金利型が向いています。現在の金利水準や自身のライフプラン、金利上昇のリスク許容度などを考慮し、将来の経済状況の予測や自己資金の有無も加味して選択することが重要です。