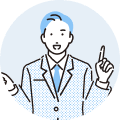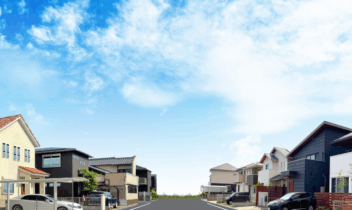- 暮らし方
- 2025.9.17
Contents
二世帯住宅の間取りタイプ
二世帯住宅とは、親世帯と子ども世帯といったように2つの家族が暮らす住宅のことで、二世帯住宅は「同居」という枠組みではなく、互いのプライバシーを守り、それぞれの世帯が独立性を持った暮らしを実現できる住宅を主に指します。
そこでまずは、二世帯住宅の暮らしや間取りの事例など、その特徴を押さえておきましょう。
完全分離型の特徴

引用元:三井ホーム
親世帯と子世帯の生活空間を完全に分け、全く別の世帯として暮らせるようにした間取りです。玄関、リビング、キッチン、浴室はいずれも別々にあり、世帯ごとにそれぞれ設けられる特徴があります。わかりやすく言うと、同じマンションの隣のお部屋で生活するようなイメージです。別々に生活しながらも、必要があればすぐにコミュニケーションを取って協力し合えます。
玄関を共用するケースもありますが、水回りや食事、リビングは完全に別々というタイプが完全分離型になります。親世帯は1階、子ども世帯は2階などの上下分離型や左右分離型の間取りがあります。
完全分離タイプだと、各世帯のライフスタイルに合わせて暮らせるので、気兼ねなく生活できます。二世帯住宅の中で、最もお互いのプライバシーをもっとも確保しやすい間取りだといえるでしょう。
また、水回りもそれぞれの世帯ごとに設けるため、気を使うことなく好きな時に使えます。光熱費や食費も別々なので支出も明確になり、費用負担で揉めることもありません。
完全分離型のメリット・デメリット

お互いの生活スタイルを尊重しつつ、困ったときは助け合いができる点が最大のメリットです。同じマンションの隣のお部屋で生活するようなイメージなので、別々に生活しながらも、必要があればすぐにコミュニケーションを取って協力し合えます。
住居を分けて生活に必要な設備を2つずつ設置するので、建築にかかる費用も高めになります。他の二世帯住宅に比べ、住宅のために確保しなければならないスペースも広くなりますので、敷地面積や延床面積など、広い土地を準備する必要があります。また、完全分離型二世帯住宅では生活空間を完全に分けているため、意識的にコミュニケーションを取らなければ交流する機会がほとんどなくなってしまいます。
完全同居型の特徴

こちらは分離型とは全く異なり、生活に必要な設備やお部屋を、親世帯と子世帯で共有する間取りになります。完全に同居するカタチになりますので、玄関、リビング、キッチン、浴室などは、いずれもひとつずつとなります。それに加え、同居する人数に応じて寝室を設けます。親世帯と子世帯が日常的に交流できるため、一緒に暮らしているという感覚を持ちやすくなるという特徴があります。「完全同居型」や「共用タイプ」と呼ばれます。寝室など個々の部屋以外はすべて共用なので、二世帯住宅のタイプ中で、最も建築費が抑えられる点が大きなメリットです。また洗濯機や冷蔵庫、テレビといった大型の電化製品も1つで済むため、生活費も抑えられます。食事や団らんといった時間は2つの家族で過ごせて、にぎやかに暮らすことができます。
完全同居型のメリット・デメリット

メリットは、今解説した通り、完全同居するカタチとなるため、建築費は余分な費用が発生しませんし、生活費用においてもコストダウンが可能になります。デメリットとして同居に最も近い形なので、生活リズムやライフスタイルが違うとお互いの生活音が気になることがあります。子どもの足音が気になったり、夜間の掃除機の音などがうるさく感じてしまったりすることもあるかもしれません。また気軽に友人や知人を呼ぶ場合も気を遣ってしまう場合があります。
そして実際に建築をする際によくあるのが、「親の意見がうるさい」など、間取りや設備の選定で意見が合わないことが発生するかもしれません。お互いに希望する家づくりが実現できないこともあるため、納得のいくまで話し合うことが大切になります。さらに、光熱費や食費なども基本的に共用になるため、負担割合が分かりにくく、二世帯住宅の中でも一番気を遣う部分が多いかもしれません。
部分共用型の特徴

引用元:積水ハウス
一部共用タイプとは、その名の通りで一部分の設備を共用する間取りになります。共用する設備は各家庭によって異なるものの、「玄関だけ」「玄関とリビングだけ」など、その家族に合った共用パターンが選べます。
「共用タイプ」と「完全分離タイプ」の中間なので、生活はある程度一緒に過ごしつつも、プライベートな空間も確保しやすくなります。また完全分離タイプに比べて、建築費が抑えられる点もメリットです。ただし共用する設備が少ないと、建築費は高くなります。
どこまで共用するかを設計時に決めなくてはならないため、お互いの意見が合わないと家づくりが難航する可能性があります。また共用する部分によっては、お互いの生活リズムが違うと、住み始めてからストレスにつながりやすい点にも注意が必要です。例えば、家族が集まるリビングを共用にしてしまうと、気を使う場面が増える可能性があります。
部分共用型のメリット・デメリット

部分共用型二世帯住宅のメリットは、一部の設備を両世帯で共有するため、ある程度近い距離で生活できます。生活空間を適度に分けているので、プライバシーを確保しながら程よい距離感を保てます。世帯によって生活の時間帯が異なる場合でも、部分共用型二世帯住宅なら他の世帯に遠慮せず、それまで通りの暮らし方の維持が可能です。また、一部の設備を共有する分、完全分離型二世帯住宅と比較すれば建築費用を安く抑えられます。1階を親世帯、2階を子世帯と分けるケースも多く、共働き世帯や子育て世帯にとってメリットが大きいと言えます。
逆にデメリットとしては、
すべての設備を分けているわけではないため、完全同居型二世帯住宅と同様、世帯ごとにどの程度の光熱費がかかっているか把握しにくくなります。そのため、どのような割合で費用を負担するかについては、あらかじめよく話し合っておく必要があります。
完全同居型二世帯住宅よりも世帯ごとの生活空間を分けやすいといえますが、完全分離型二世帯住宅ほどしっかりとプライバシーを確保できるわけではありません。ある程度は同居する他の世帯への配慮も必要となります。
二世帯住宅の間取りを決める際のポイント
ではここからは、二世帯住宅を建てる際に気をつけておきたい間取りづくりのポイントをご紹介します。建てた後に後悔しないよう心がけましょう。
家族構成とライフスタイルの考え方

完全同居型や一部共用型の二世帯住宅では、両世帯で共有する設備があります。そのため、家事を分担しながら作業しなければならない場面も少なからず出てきます。そのため二世帯住宅の間取りを考えるときは、家族構成や家族のライフスタイルをしっかりと考える必要があります。
実際にどのように家事を分担するか具体的にイメージしておくといいでしょう。
それぞれの世帯の生活スタイルも考慮しながら、協力して家事を進めやすいレイアウトを考える必要があります。特に、キッチンをはじめとする水回りをスムーズに利用できるように工夫するといいでしょう。
将来的な家族構成の変化を見据える

二世帯住宅では2つの世帯が共同で暮らすため、プライバシーをどのように確保するかがとても大きな問題になります。特に、世帯によって活動する時間帯が異なる場合、小さな物音でもストレスに感じる場合があります。
また子どもの成長、親の介護など、ライフステージによって様々な生活環境の変化があります。
工夫ポイントとしては、例えば上下階で親世帯と子世帯の生活空間を分ける場合、水回りの設備は上下階で同じ位置になるようにしましょう。こうした工夫をすることで、お風呂、洗面、トイレなどの水回りを使用しても、他の世帯で音が気になりにくくなります。
親世帯・子世帯それぞれの希望を調整

親世帯と一緒に暮らす上で、親世帯の老後の生活に備えることもとても重要な要素になります。親世帯が使用する生活空間や共有のスペースは、バリアフリーになるようデザインすることで老後の介護や生活補助がしやすくなります。
現時点では、親世帯が元気だとしても、将来的には介護が必要になる可能性もあります。二世帯住宅を建てるときは将来を見通して設備や間取りを検討し、長く安心して暮らせるようにすることをおすすめします。
二世帯住宅の費用相場と支援策の概要
ではここからは、二世帯住宅の費用相場などについて見ていきましょう。また、地域や行政によっては住宅ローン控除などの支援策を行っていることもあります。しっかりと見ていきましょう。
二世帯住宅の費用相場(坪単価70万~120万円)

ハウスメーカーで建てる注文住宅の場合、坪単価は1坪当たり75万~100万円ほどが相場といわれています。ただし二世帯住宅の場合、お風呂やトイレ、キッチンなど、どの設備を共用にするかによって建築費用に大きな差が出てきます。ちなみに二世帯住宅でも、完全分離タイプが一番建築費の相場が高くなります。目安としては、設備仕様を比較した場合、共用タイプ(完全同居型)で2階トイレを設置した場合は単世帯住宅に比べて25~35万円前後、一部共用型でキッチン・トイレを別で設置した場合80~100万円前後、完全分離型で玄関、玄関収納、キッチン、洗面台、浴室など別で設置した場合200~240万円前後がプラスになります。
建築費の相場ですが、間取りにもよるものの3,200万~4,000万円といわれています。二世帯住宅の場合、建築費を親世代に援助してもらえる点も大きなメリットとなるため、建築費の負担割合についても建てる前にしっかり話し合いをしておきましょう。
住宅ローン控除・相続税特例などの支援策

二世帯住宅には、建てるときや居住している間、税金の優遇措置があります。
住宅の新築時には、不動産取得税や固定資産税などの軽減措置を受けることができます。二世帯住宅を新築するときには、登記内容にかかわらず、いくつかの要件を満たすことで二戸分の軽減措置を受けられる場合があります。
軽減措置が受けられる二世帯住宅の要件は、「構造上の独立性」「利用上の独立性」を満たしていることです。具体的には、各世帯が専用の「玄関」「キッチン」「トイレ」を持ち、独立して生活できること、各世帯をつなぐ廊下などは、鍵付きの扉などで仕切ること、などになります。
要件は、各地方自治体によって異なる場合もありますが、要件を満たして二戸分と認められれば、不動産取得税や固定資産税などの軽減措置が受けられます。
そして居住している間は、住宅ローンの残高に応じて、所得税もしくは住民税が控除されます。
まとめ
さて今回の記事では「二世帯住宅の相場」や「二世帯住宅の間取り選び」についてご紹介してまいりましたが、最後までご視聴いただいたみなさまはいかがでしたでしょうか?
- 二世帯住宅の間取りタイプ
- 二世帯住宅の間取りを決める際のポイント
- 二世帯住宅の費用感と支援策
などついて解説してまいりました。
これから住宅の購入や建築を検討されている方は、是非こちらの記事を見て、お家づくりを進めてみてください。
まだ、この記事を細部まで見られてない方は、ぜひ必要なポイントだけでもいいのでご覧いただけると幸いです。
きっと家づくりのお役に立てる工夫を学ぶことができると思います。
今後の家づくりの参考にされてみてください。
今後こちらのチャンネルでは、注文住宅や新築一戸建てを検討する上で、「役に立つ情報」や「知って得する家づくりのポイント」などを随時配信する予定です。
一生に一度のマイホームを「失敗しない」ために、様々な情報を配信できればと思います。
***
まるっと住まいの窓口 では
理想の家を実現するために、
オンライン住宅相談で住宅のプロに中立の立場で直接相談ができます!
また、埼玉、茨城、群馬、栃木エリアで
モデルハウスを100軒以上、家の専門家を100人以上ご紹介しています!
ぜひご活用ください。
この記事に関連したよくある質問
- 完全分離型の二世帯住宅を建てるとどれくらい費用がかかりますか?
-
完全分離型の二世帯住宅を建てる費用は、一般的に約3,000万円から5,500万円程度が相場です。このタイプはキッチン、浴室、玄関などの設備が二世帯分必要となり、3つのタイプの中で最も建築費用が高くなります。費用は坪数、地域、設備仕様、間取りなどによって大きく変動するため、具体的な金額を知るにはハウスメーカーや工務店に相談し、概算見積もりを取ることが重要です。
- 二世帯住宅には最低でも何坪必要ですか?
-
二世帯住宅で最低限必要となる延べ床面積は、世帯間の共有スペースの程度によって異なりますが、家族構成やライフスタイルを考慮すると、40坪以上が目安です。具体的には、完全同居型や一部共有型なら30坪台後半~40坪台から可能ですが、完全分離型なら50坪以上が推奨されます。
- 二世帯住宅の平均的な床面積はどのくらいですか?
-
二世帯住宅の平均的な床面積は、40坪~50坪程度が多いですが、完全に分離するタイプでは60坪~70坪が目安になります。必要な坪数は、二世帯住宅のタイプ(完全共有型、一部共有型、完全分離型)や家族構成、部屋数によって異なるため、間取り係数を活用してシミュレーションすることが推奨されます。
- 40坪の二世帯住宅を建築する場合の費用目安はいくらですか?
-
一般的に約3,000万円から5,500万円程度が相場です。
- 部分共用型を選ぶ際の注意点は何ですか?
-
部分共用型を選ぶ際は、共有部分の選定と配置、生活音への配慮、プライバシーの確保、そして家族間の意思疎通に注意が必要です。特に、キッチンや浴室などの水回り、リビング、玄関などの共用する場所を決める際は、建築費用だけでなく、将来の生活リズムの違いや家族の人数を考慮し、ストレスやトラブルを避けるための間取りの工夫が重要です。
- 二世帯住宅で利用できる住宅ローン控除はありますか?
-
住宅ローン減税 「共有登記」「区分登記」ならば、親世帯・子世帯それぞれが住宅ローン控除を受けられます。 なお、住宅ローン減税が適用されるのは、「自分の居住場所」だけです。 二世帯住宅で「共有登記」の場合、親世帯・子世帯で居住空間を分けることになります。
- 将来、どちらかの世帯を賃貸に出すことは可能ですか?
-
可能です。ただし、賃貸に出しやすいのは「完全分離型」の二世帯住宅であり、設計段階から将来の賃貸併用を視野に入れて間取りや設備を決めることが重要です。玄関や水回りなどがそれぞれ独立しているため、他人への賃貸もスムーズでトラブルを防ぎやすく、大規模なリフォームなしに一世帯分を賃貸に出せます。